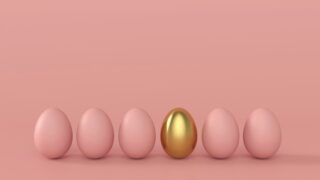テレビやネットでそんなニュースを見ても、ついチャンネルを変えてしまうかもしれません。
ですが、実はそのニュース、あなたがスーパーで支払う金額や、
大切に貯めている将来のお金に、直接つながっているんです。
今回は、2025年8月26日に報じられた3つの大きなアメリカのニュースを取り上げ、
私たちの毎日の生活に「どう影響するのか」を、誰にでもわかるように、身近な例で紐解いていきます。
1.大統領 vs 中央銀行トップ?!「FRB理事解任」騒動で、あなたのお金の価値が変わるかも
【何が起きているの?】
2025年8月25日、アメリカのトランプ大統領が、FRB(アメリカの中央銀行)のクック理事の解任を発表しました。
しかし、当のクック理事は「大統領に私を解任する権限はなく、辞めるつもりはありません」と強く反論しています。
【なぜこれが大問題?】
FRBは、日本の日本銀行(日銀)のように、国のお金の価値や流れをコントロールする、とても重要な機関です。
その大きな役割のひとつに、政治から独立して判断を下す「独立性」という原則があります。
今回の出来事は、その大原則が揺らぎかねないとして、
世界中の投資家たちが「アメリカの経済は大丈夫?」と不安になっています。
【私たちの生活への影響は?】
この「不安」が、具体的にお金の動きを変えています。
-
輸入品が安くなるかも?(円高)
不安を感じた投資家は、比較的安全とされる「円」を買う動きを強めています。これにより「ドル安(円高)」が進む可能性があります。
円の価値が上がると、海外の製品を安く買えるようになります。
-
身近な例:欲しかったアメリカブランドのiPhoneや洋服が、少しだけ安く手に入るかもしれません。
-
海外旅行に行く人にとっても、旅費を抑えられるメリットがあります。
-
-
NISAやiDeCoの資産が減るリスクも(株安)
一方で、経済の先行きが不透明になると、企業の株を売る動きも活発になります。これが世界的な株安につながると、日本も影響を免れません。
-
身近な例:証券口座で積立NISAやiDeCo、株式投資をしている人は、自分の資産の評価額が一時的に減ってしまう可能性があります。
-
このように、大統領と中央銀行の対立という遠い国のニュースが、
スマホの値段や、私たちの老後のための大切な資産に直接影響してくるのです。
2.ネットサービスや輸入品が値上がり?「デジタル課税」をめぐるアメリカの警告
【何が起きているの?】
アメリカのトランプ大統領が、「デジタル課税を続けるなら、その国からの輸入品に関税をかける」と警告しました。
デジタル課税とは、簡単に言うと、国境を越えてサービスを展開する巨大IT企業に対して、その国が独自にかける税金のことです。
【なぜこれが大問題?】
アメリカにはGoogle、Amazon、Meta(旧Facebook)といった世界的なIT企業がたくさんあります。
アメリカからすれば、この税は「うちの国の企業を狙い撃ちしている」と見え、それに対する報復として「関税」というカードを切ろうとしているのです。
関税がかけられると、その国からアメリカに輸出される製品の値段が上がり、ビジネスがしにくくなります。
【私たちの生活への影響は?】
この問題も、巡り巡って私たちの家計に影響します。
-
ワインやチーズが値上がりするかも?
もしヨーロッパの国々がデジタル課税を続けた場合、報復関税の対象になる可能性があります。-
身近な例:スーパーでいつも買っているヨーロッパ産のワインやチーズ、パスタなどの輸入品が、関税の影響で少し高くなるかもしれません。
-
-
iPhoneやネットサービスの利用料が上がるかも?
もしIT企業が各国で支払う税金の負担が増えた場合、そのコストを製品やサービスの価格に上乗せする(転嫁する)可能性があります。-
身近な例:iPhoneなどのガジェット製品や、私たちが日常的に使っているクラウドサービス、動画や音楽のサブスクリプションサービスの月額料金が、将来的に値上がりするかもしれません。
-
と思っていたら、ある日突然、いつもの買い物の合計金額が上がっている…
という形で、私たちの生活に跳ね返ってくる可能性があるのです。
3.スマホや薬が安定供給へ?「日米通商交渉」の良いニュース
【何が起きているの?】
日米間で、いくつかの重要な分野で協力を深める交渉が進んでいます。
具体的には、半導体、抗生物質(医薬品)、レアアース(希土類)といった、私たちの生活に欠かせない物資の安定供給を目指すものです。
【なぜこれが大事なの?】
これらの物資は、特定の国に生産を頼っていることが多く、国際情勢によっては供給が不安定になりがちです。
日本とアメリカが協力することで、いざという時でもお互いに供給しあえる体制を作ろうとしています。
【私たちの生活への影響は?】
これは、私たちの暮らしの「安心」に直結する話です。
-
スマホや家電が安定して手に入る
半導体は、スマートフォンやパソコン、ゲーム機、自動車など、あらゆる電子機器の心臓部です。この供給が滞ると、製品が品薄になり価格が高騰します。-
身近な例:日米協力によって半導体の供給が安定すれば、iPhoneの新型や人気のゲーム機が「品薄でなかなか買えない」といった事態が起こりにくくなり、価格も落ち着くことが期待できます。
-
-
いざという時の医薬品不足が解消されるかも
特定の医薬品、例えば抗生物質などの供給が滞ると、必要な時に治療が受けられないという深刻な事態につながりかねません。-
身近な例:日米で協力して医薬品の供給網を強化することで、「病院や薬局に行っても、いつもの薬がない」という不安が減り、安心して医療を受けられるようになります。
-
-
電気自動車(EV)がもっと身近になるかも
レアアースは、電気自動車のモーターやバッテリーに不可欠な資源です。-
身近な例:レアアースの安定確保が進めば、今後ますます普及が見込まれる電気自動車の生産が安定し、価格も手ごろになる可能性があります。
-
まとめ:世界の経済と、私たちの財布はしっかりつながっている
今回ご紹介した3つのニュースは、一見すると「遠い世界の話」に聞こえるかもしれません。しかし、
-
為替の変動は、iPhoneの価格や海外旅行の費用に。
-
関税の問題は、スーパーで買う輸入食品やネットサービスの料金に。
-
貿易の協力は、薬や家電製品、自動車といった生活必需品の安定に。
このように、すべてが私たちの身近な消費や生活コストにダイレクトにつながっています。
【私たちにできる備えは?】
こうした世界の動きから家計を守るためには、いくつかの視点を持つことが大切です。
-
価格上昇への備え:輸入品の値上がりが気になる時は、美味しい国産品を探してみるなど、代替品に目を向けるのも一つの手です。また、必要なデジタルサービスを見直したり、家計簿アプリで支出を「見える化」したりするのも効果的です。
-
為替や金利の変動に対応:円高の時には海外製品を買う、円安の時は国内旅行を楽しむなど、為替の動きを意識すると賢くお金を使えます。また、金利が上がりそうな時は、住宅ローンの借り換えを検討するのも良いでしょう。
-
資産を守る視点を持つ:市場の急な変動に備え、積立投資などで投資先や時間を分散させることがリスク軽減につながります。
世界のニュースに少しだけアンテナを張っていると、
「この値上がりは、あのニュースが関係しているのかも?」
と、物事の背景が見えてきます。
そう思うだけで、経済の動きが少し身近に感じられるようになるはずです。
(2025年8月26日 記)