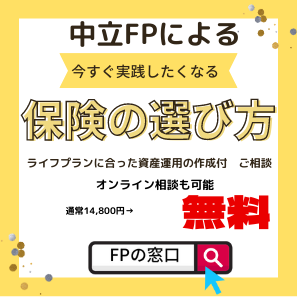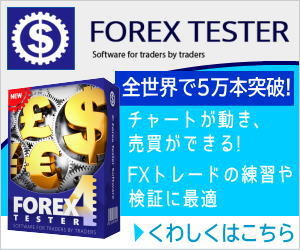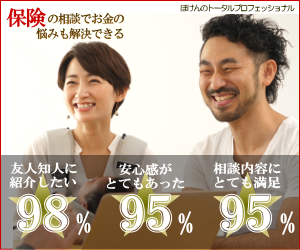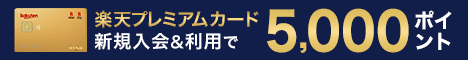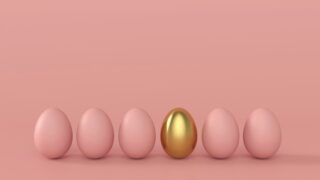「毎月コツコツ貯金しているのに、通帳に記帳された利息を見てガッカリした……」そんな経験はありませんか?
「昔は銀行に預けておくだけでお金が増えた」という話を聞くと、今の時代の厳しさを感じて不安になるのも無理はありません。
実は、今の日本において「ただ銀行にお金を預けているだけ」では、残念ながら大切なお金はほとんど増えません。
それどころか、気づかないうちに「お金の価値」が実質的に目減りしている可能性さえあります。
この記事では、なぜ銀行預金ではお金が増えないのか、その理由を3つのポイントから紐解いていきます。
読み終える頃には、お金の不安の正体が分かり、今から何をすべきかが明確になっているはずです。
理由①:驚くほど低い「金利」の現実
まず一番の理由は、なんといっても「金利(きんり)」が極めて低いことです。
金利とは、銀行にお金を預けたお礼として受け取れる「利息」の割合のこと。
この金利が高いほど、私たちの手元に残る利息も多くなります。
100万円預けても利息はたったの10円
現在の普通預金の金利は、多くの銀行で「年0.001%」程度。
これがどれくらいの数字か、具体的にイメージしてみましょう。
🔷100万円を1年間預けても、もらえる利息はたったの「10円」(※税引き前)
30年ほど前の1990年頃は、金利が6%を超えていた時期もありました。
当時は100万円を預ければ、1年で6万円もの利息がついていたのです。
理由②:見えない敵「インフレ」でお金の価値が減っている
「利息が少なくても、元本(預けた金額)が減らなければ安心」と考える方も多いでしょう。
インフレとは、モノの値段が上がり、相対的にお金の価値が下がってしまうこと。
通帳の数字は減っていなくても、「そのお金で何が買えるか(購買力)」が減ってしまっているのです。
マックの価格でわかる「実質的な目減り」の正体
| 年月 | ハンバーガー単価 | 状況 |
| 2020年 | 110円 | 500円で4個買えた |
| 2025年現在 | 190円〜200円 | 500円で2個しか買えない |
5年前、銀行に預けた500円で4個買えたはずのものが、今は2個しか買えません。
これは、預けている間に「500円の価値」が半分近くまで下がってしまったことを意味します。
銀行預金はこの物価上昇のスピードについていけないため、知らず知らずのうちに資産が目減りしていくのが現状です。
理由③:銀行破綻のリスク「ペイオフ」も知っておこう
もう一つ、私たちが知っておくべきは「ペイオフ」という制度です。
銀行に預けたお金は、実は全額が永久に保証されているわけではありません。
もし銀行が破綻した場合、保護されるのは「1つの銀行につき、1人あたり元本1,000万円までとその利息」と決まっています。
【解決策】お金を「守る場所」と「育てる場所」に分ける
ここまで読んで、「じゃあ、どうしたらいいの?」と不安を感じたかもしれません。
大切なのは、お金を「守るための貯金」と「育てるための投資」に分けることです。
まずは「生活防衛資金」を確保する
🔶目安:生活費の3ヶ月〜半年分
利息がつかなくても、「いつでも引き出せる安心感」は心の安定に不可欠です。
将来のお金は「新NISA」で育て始める
| 項目 | 銀行預金(貯金) | 投資(新NISAなど) |
| 主な目的 | 今すぐ使う・絶対に守る | 将来のために大きく育てる |
| メリット | いつでも引き出せて安心 | 物価高(インフレ)に強い |
| 初心者へ | 【必須】生活費の半年分 | 【推奨】余剰資金で少額から |
まずは少額から試してみたいという方には、初心者へのサポートが手厚く、100円から投資ができる「SBI証券」や「楽天証券」がおすすめです。
最短5分でスマホから口座開設の申し込みができますよ。
私はNISA口座は楽天証券を利用しています!アプリも見やすく管理もしやすいです。
[ >> 楽天証券で無料口座開設をして「安心の未来」を作る ]
まとめ:不安を安心に変える「はじめの一歩」
銀行預金がなぜ増えないのか。
その理由を知ることは、これからの時代を自分らしく、安心して生きていくための大きな第一歩です。
このブログが大切にしているのは、単にお金を増やすことだけではありません。
お金の不安を正しく理解し、コントロールすることで、あなたの人生に「自由・選択肢・安心」という、通帳には載らない幸せを増やしていくことが本当の目的です。
まずは現状を知り、無理のない範囲で少しずつ、新しい一歩を踏み出してみましょう。
あわせて読みたい:より具体的なステップへ
🔶不安な私の自分年金|新NISAで日本高配当株を分散して自分で組む方法
🔶インデックス投資とは?初心者女性でも失敗しない始め方と銘柄選び
🔶米国高配当ETFどれがいい?新NISAで初心者が失敗しない4銘柄比較
🔶【新NISA対応】投資の基本が5分でわかる!難しい用語を徹底解説
情報提供の目的: 本ブログは、投資に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の投資助言や推奨を行うものではありません。
投資は自己責任:投資信託の購入や売却に関する最終的なご判断は、読者ご自身の責任において行ってください。
投資リスクについて:投資にはリスクが伴い、元本を割り込む可能性があります。
過去の運用実績は、将来の成果を保証するものではありません。
ご自身での確認:投資を行う際は、必ずご自身で十分な調査を行い、各商品の目論見書等をご確認ください。
必要であれば専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
情報の鮮度:本ブログの情報は執筆時点のものであり、将来的に変更される可能性があります。
最新の情報は、各金融機関の公式サイト等でご確認ください。
株式投資の管理アプリ「カビュウ」を使っています。
証券口座を連携するだけで、過去の資産推移がグラフで見やすく、自分の投資傾向も分析できます。まだ使っていない方、私の紹介コードでプライムプランを最大2ヶ月無料でお試しいただけます。
紹介コード:【ShVq】
(口座連携後、30日以内に設定から入力ください)https://kaview.jp/
※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。
広告を経由せずにご購入を希望される場合は、各サービスや商品の公式サイトをご利用ください。